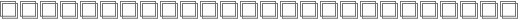
熊本大学合唱団創立60周年記念演奏会
2005.12.10
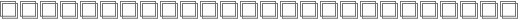
| 指揮者 | 藏岡多可士 | |
| 独奏者 | 千葉慶子(Sop) 閘 優子(Alt) 大島 博(Ten) 岩本貴文(Bas) |
|
| 演奏曲 | バッハ | ミサ曲ロ短調 |
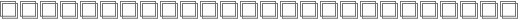
| コンサートマスター | 大宮伸二 |
| 第1ヴァイオリン | 浦中有紀、定永明子、瀬畑健雄 東家容子、益田久美 |
| 第2ヴァイオリン | 大宮協子、岡本侑子、清永健介 多賀美紀、山口祐子、山下純子 |
| ヴィオラ | 和泉希代子、太田由美子、田代典子 中澤康子、山口みゆき* |
| チェロ | 坂本一生、関 栄、瀬畑むつみ、東家隆典、松本幸二 |
| コントラバス | 歳田和彦、中川裕司* |
| フルート・ピッコロ | 泉 由貴子、中澤邦男 |
| オーボエ・オーボエダモーレ | 高橋献一*、松本聡子*、吉田千草 |
| ファゴット | 柴田義浩、星出和裕 |
| ホルン | 伊藤友美 |
| トランペット | 出口文教、福島敏和、三原 丹* |
| ティンパニ | 福島 好* |
| チェンバロ | 坂田孝子* |
*賛助
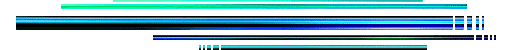
ミサ曲ロ短調BWV.232(バッハ)この曲は、1748年の8月から1749年の10月にかけてライプツィヒで作曲された。当時すでに60歳を越えていたバッハは、著名な音楽家で構成される「ミツラー協会」の会員に迎えられるなど、東部ドイツに おいて一定の評価を得るようになっていた。この作品は、そうした成熟と完成の時期を代表する大作で あり、バッハの教会音楽のなかでも最も重要なものに数えられる。近年の研究では、彼の事実上最後 の完成作とも目されており、その意味でも興味深い(これまで最後の作品と考えられていた「フーガの 技法」は、1749年6月以前に書かれたという)。実際自筆楽譜には、体力の衰えからと思われる筆跡の 乱れが散見され、1750年7月の死を暗示している。 「ミサ曲ロ短調」は、様々な点において特異な作品である。少なくともこの曲は、教会における上演を 前提として書かれたものではない。第一に、聖トーマス教会(ルター派)のカントルを務めるバッハが、 カトリックのラテン語ミサ(全曲)を作曲するということ自体、不自然な印象を与える。もちろん外部から の個人的依頼の可能性はあるが、そうした場合においても、計2時間という上演時間は、一般的なミサ の枠を大幅に越えている。各曲の楽器・声楽編成にもばらつきがあり(木管楽器やソロ・合唱の規模)、 演奏上のプラクティカルな制約を顧慮した形跡が見られない。これは「大いなる実際家」であったバッハ としては、かなり異例のことである。 それで彼は、晩年に至ってなぜ上演する見込みもない大作を書き上げたのだろうか。上に挙げた条件 ないし状況は、バッハが職務とは別の「音楽的遺言」を書く意識を持っていたことを伝えている。彼は 1740年代以降、旧作の編纂や保存に力を入れ始める。それは「平均律クラヴィーア曲集第2巻」や「18 のコラール」などの体系的曲集としてまとめられるが、「ミサ曲ロ短調」も複数の既存作品を土台とする 編纂的様相を示している。すなわち第3部「サンクトゥス」の原曲は、ライプツィヒ時代初期の1724年に さかのぼり、第1部も「ミサ」(キリエとグローリア)も、1733年にバッハがザクセン選帝候に宮廷作曲家 の称号を願い出た時の献呈作なのである。第2部「ニケーア信条」と第4部「ホザンナ、ベネディクトゥス、 アニュス・デイ、ドナ・ノビス・パーチェム」も、様々なカンタータからのパロディ(改作)に当たる。このため 以前のバッハ研究では、「ミサ曲ロ短調」は、4つの個別的な作品の集合に過ぎないとされてきた。 しかしバッハはこの作品で、明らかに通作的で完結したミサを書くことを意図していた。全体はニ長調/ ロ短調を中心に組織され、調性構造には一貫性が感じられる。形式の点でも、第6曲の楽想が終曲( 第25曲)で再登場するなど、循環的な構成が打ち出されている。総じてバッハは、ここで持てる作曲 技法の限りを尽くしたと言えるだろう。パッサカリアや厳格対位法、協奏形式、イタリア的アリアなどの 多彩な書法は、高度な技巧と壮麗さの点で、まったく比類のない次元に達している。5人のソロや、5声 から8声(2重合唱)に至る大規模な合唱も含めて、バッハはこの曲で一種の芸術的総決算を行ったの である。ラテン語歌詞への作曲も、地域的・時代的な性格を示すドイツ語カンタータ(ドイツ語による宗教 曲は当時「流行的現象」とみなされていた)を越える、高い価値を狙ってのことと思われる。彼がわざわざ ミサの形式を採用したのは、ラテン語通常文の持つ恒常性・普遍性のためなのである。 もっともバッハはここで、カトリックの厳格なミサ形式に従っていない。一般的なミサは、キリエ、グロー リア、クレド、サンクトゥス、アニュス・デイの5部構成を取るが、ここでは独自の4部構成が採用されてい る。さらに典礼文そのものも、ローマ教会のそれとは完全に一致していない。バッハはルター派教徒と してカトリック典礼文に作曲したわけだが、こうした旧来の形式に捕らわれない形式を採用することに よって、宗派の境を越えた教会音楽の創造を目指したのかもしれない。その願いは、バッハの死後250 年経過した時代において、見事に成就したと言える。すなわちこの曲は、宗派の違いばかりかキリスト 教そのものを越えて受け入れられ、世界中の人々に広く愛されているのである。 |
![]()