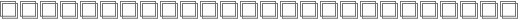
第15回演奏会
2002.4.7
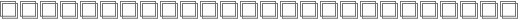
| 指揮者 | 藤崎凡 | |
| 独奏者 | ||
| 演奏曲 | ハイドン | 交響曲第103番変ホ長調「太鼓連打」 |
| シューベルト | 交響曲第9番ハ長調「ザ・グレイト」 | |
| パンフレット | ||
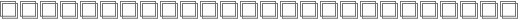
| コンサートマスター | 清永健介、廣瀬 卓 |
| 第1ヴァイオリン | 泉 勇気、大宮伸二、岡本侑子、定永明子、東家容子 古市敬子 |
| 第2ヴァイオリン | 大宮協子、清永育美、田中 唱*、丁 睦美、中澤康子 山口祐子、山下純子 |
| ヴィオラ | 和泉希代子、太田由美子、田代典子、辰野陽子* |
| チェロ | 石垣博志*、関 栄、東家隆典、松本幸二 |
| コントラバス | 桑原寿哉*、歳田和彦、中川裕司* |
| フルート | 田島公敏、中澤邦男 |
| オーボエ | 荒田優子*、石田栄理子*、橘 徹 |
| クラリネット | 岡村クミ、府高明子 |
| ファゴット | 柴田義浩、星出和裕 |
| ホルン | 伊藤友美、後藤 滋* |
| トランペット | 出口文教、福島敏和 |
| トロンボーン | 児嶋美穂*、寺本昌弘*、右田順二* |
| ティンパニ | 福島 好* |
交響曲第103番変ホ長調Hob.Ⅰ-103「太鼓連打」(ハイドン)ハイドンは彼最後の交響曲群となった3曲に、無限とも思えるような創意の異なる面を示そうとした。この第103番の穏やかな導入部の構造は、18世紀に作曲された一般の交響曲のどの作品よりも 複雑に、また深い層で主部のアレグロ・コン・スピーリトに結び付けられている。また、単一主題による 終楽章の構造はベートーヴェンの第5交響曲の第1楽章が現れる以前のどんな作品よりも堅実な構造 と統一性をもつものである。 俗謡の旋律が意識的に導入されていることも、この交響曲の特徴といってよいだろう。そして、さらに 重要なことは、そうした俗謡の旋律をハイドンがいかに見事に古典派の様式の語法に組み入れている かということである。 独奏ヴァイオリンの長いソロは、オペラ・コンサートのオーケストラの卓越した首席奏者であったヴィオ ッティのために書かれたものに違いない。 第1楽章の導入部はティンパニのロール打ちで始まる。ハイドンはそこに「ソロ」および「イントラーダ」 (導入部)と記したが、強弱の記号は書き入れていない。 しかし、ザロモンによるピアノ・トリオ編曲版では漸強、漸弱の松葉が書かれていて、それが伝統的な 演奏法として慣用化されていた。その上、ザロモンによるもう一つの五重奏編曲版ではフォルテッィシモ と記されており、長いデクレッシェンドがそれに続いている。 今日の指揮者は、この「太鼓連打交響曲」を演奏する際、ザロモンによって残された二様の解釈の間 で選択を迫られているのである。 ファゴット、チェロ、コントラバスのユニゾンで、荘重な太い歩みの旋律が続く。この導入部の主旋律は 主部の展開部でも用いられており、導入部そのものがコーダの前で再現する。また、その動機は第2 主題の冒頭をも作る。すなわち、導入部と主部とは従来考えもおよばなかった程に有機的な関係を保つ ようになっていく。 第2楽章はアンダンテ・ピウ・トスト・アレグレットでハ短調。二つの主題による変奏曲である。ここでハ イドンは東欧の旋律を用いたが、彼は異国的なこの旋律がいかに効果的な主題に成り得るかを示すこ とで大きな満足を覚えたことだろう。 第3楽章のメヌエットでも民謡風の素材は十分に生かされる。ここで登場するのはオーストリアのヨー デルで、それは優美な芸術音楽に装いを変えるのだ。トリオではクラリネットがその音色を十分に発揮 するが、反面、初期のドイツ版の楽譜ではメヌエットのクラリネットは完全に除外されている。 第4楽章はアレグロ・コン・スピーリトで、ソナタ形式ではあるが、展開部の第1主題が主調で現れるの でロンドに近い性格を示している。ホルンの牧歌的な導入部の後、このホルンの動機の上でヴァイオリ ンが第1主題を快活に歌い出す。そして、この主題を扱った経過部の後に、楽章の後半を大きく支配す る第2主題が現れる。 第2主題の開始部は第1主題とよく似通っている。あるいは単一の主題による長大な楽章の創造を示 したものともいえようか。 ともかく、この「太鼓連打」を含む後期6曲の「ザロモン交響曲」は、過去の音楽的創造の偉大な総括 であり、他方では同時代の、そして後に続く作曲家たちのための無限に広がる新しい展望を開いた作品 なのであった。 中でもベートーヴェンはこの栄光に満ちた交響曲の伝統を継承し、さらに発展させるのである。 |
交響曲第9番ハ長調D.944「ザ・グレイト」(シューベルト)この曲は「第7番」と呼ばれることがあり、希に「第10番」説を主張する人が存在し、そして「第8番」と なる可能性さえある。 この曲が完成したのは、シューベルト死の年の1828年の3月。10年後の初演のときには、これより 前にでき上がっていたロ短調「未完成」はまだ知られていなかった。「第7番」といわれることの根拠の ひとつにこのことも挙げられている。 さて、シューベルトは死の年、友人に「歌はもうやめにした。これからはオペラと交響曲だけにする」 云々といったという。そしてでき上がったのがこの大交響曲である。同じハ長調という調をもっていても、 以前の第6番D589と比べれば、その倍近い演奏時間を要し、規模の雄大さ、のちのブルックナーを予 見させる宇宙的な広がりと男性的な迫力、美しいメロディなどすべての点でまさっている。とにかくこの 時代にこのような途方もない(と10年後にこの曲を発見したシューマンには思えた)曲を作った音楽家 はシューベルト以外にはいなかった、確かに、全体のまとまりといった点からいえば、もう少し推敲の余 地がありそうな部分もなくはないが、シューマンをして「天国的な長さ」と言わしめたこの曲の評価と人気 は、今や「未完成」を超えるものとなっている。 もう少し詳しくこの曲の成立をみてみよう。実はシューベルトがいつこの曲を書き始めたのかはあまり はっきりしていない。焼失したとされる「グムデン・ガシュタイン交響曲」がこの曲ともし同じもの、または その前身だとすれば、1825年夏には着手されていた可能性がある、というのが現段階でのシューベル ト研究者の推論である。それはともかく、この曲もまた作曲後10年間、演奏されないままシューベルトの 実兄フェルディナントの家で眠ってしまう。1838年シューマンがこれを発見し、同年3月21日メンデルス ゾーンの指揮で(ただし、短縮版であった)初演され、ようやく世の人に知られるようになった。 第1楽章、アンダンテ〜アレグロ・マ・ノン・トロッポ、ハ長調。ホルンが森の奥から呼びかけるようなロ マンティックなメロディを柔らかに奏して始まる。木管がこれを受け継ぎ、弦が細かく音を刻みながら上昇 していき盛り上がる。2小節の絶妙な転調部の後の第2主題は意外にもホ短調。木管による東洋的な響 きさえする軽快なものである。変イ長調で始まる展開部から先は雄大で、そのスケールの大きさは後の ブルックナーを思わせる。 第2楽章、アンダンテ・コン・モート、イ短調。大規模な三部形式で、中間部の夢幻の境地をさまようよう な部分と、神秘的な弦の刻みの上に奏でられるオーボエの美しいメロディとの対比が鮮やかで、おそらく シューベルトの全器楽曲中でも、「未完成」の第2楽章と双璧の大傑作である。曲は短調と長調の間を微 妙に揺れ動き、名残惜しそうに消えていく。 第3楽章、アレグロ・ヴィヴァーチェ、ハ長調。雄大なスケルツォで、大地が振動するような響きで始ま り、優美なメロディをその後に従わせる。イ長調のトリオは弦の波動の上に木管が微妙に三度転調で揺 れ動く一度聴いたら忘れられない可憐なもの。 第4楽章、アレグロ・ヴィヴァーチェ、ハ長調。威張っているようなものものしいトゥッティで始まる。この 主題は湧き上がるような推進力をもち、ト長調の人なつっこい第2主題と対照的。この楽章だけで1155 小節に及び、ハイドン風の軽妙なフィナーレの対極ともいうべき壮大な響きで押しまくり、ハ長調の輝かし い終結へ向かって突進していく。 |